猫の換毛期は、春と秋の季節の変わり目に訪れ、通常は数週間から1ヶ月程度続きます。
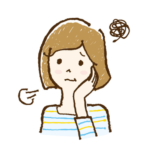
猫の毛ってこんなに抜けるの…?
と、思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、室内飼いの猫は気温や照明の影響で換毛期が長引くことも。
抜け毛が増えると掃除が大変になるだけでなく、毛玉の原因にもなるため、適切な対策が必要です。

この記事は以下のような人にオススメ!
- 猫の換毛期はいつまで続くのか知りたい人
- 猫の毛が抜けすぎて少し不安になっている人
- 抜け毛対策法を知りたい人
本記事では、猫の換毛期はいつまで続くのか?を詳しく解説し、長引く原因や抜け毛対策まで徹底的にご紹介します。
愛猫との快適な生活のために、できるケアを今すぐ始めましょう!
猫の換毛期はいつまで続く?基本的な時期と目安を解説

猫の換毛期は、一年のうち春と秋に訪れる毛の生え変わりの時期です。

換毛期は猫にとって重要な体調管理の一環であり、飼い主にも適切なケアが求められます。
では、換毛期は具体的にいつから始まり、いつまで続くのでしょうか?
一般的な猫の換毛期の時期は?季節ごとの変化
猫の換毛期は、主に以下の2つの時期に分かれます。
- 春(3月~5月頃)
- 秋(9月~11月頃)
このように、換毛期は季節の変化に応じて年に2回訪れます。
春には、ふわふわとした厚い冬毛が抜け落ち、軽く通気性の良い毛に変わります。
秋には、寒さに備えて厚みのある冬毛が生えてきます。
しかし、換毛の程度や期間は個体差があり、同じ猫でも年ごとに異なることもあります。
室内飼いの猫の換毛期は通常とは違う?

いくら換毛期とはいえ、こんなに毛が抜けるものなの?
このように感じたことがある方も多いと思います。
室内飼いの猫は、外気に直接触れる機会が少ないため、換毛期の毛の抜け方が通常と異なる傾向があります。
特に、以下のような特徴が見られることが多いです。
- 換毛期の時期感がはっきりしない
- 抜け毛が増える
換毛期がはっきりしない
室内飼いというのは、一年の中で温度差を感じにくい環境です。
そのため、一年中少しずつ毛が抜けることが多く、明確な換毛期がない場合があります。

換毛期が終わったかな?と思っても、じわじわ毛が抜けていくこともあります!
抜け毛が増える
エアコンの使用によって気温が一定に保たれると、体が換毛期のリズムを感じにくくなります。
室内飼いをしている猫は、種類によっては換毛期ごとに抜ける毛が通常よりも多くなることがあります。

室内飼いの猫も換毛の影響を受けることは変わりません。
そのため、季節に関係なく抜け毛対策を行うことが求められます。
抜け毛がひどい!換毛期トラブルの原因と対処法
猫の換毛期は、通常よりもかなり毛が抜けやすくなります。

極端に抜け毛が増えたり、換毛期が長引いたりする場合は、換毛期以外に何かトラブルが起きている可能性があります。
抜け毛が多い・換毛期が長いときに考えられる健康トラブル
換毛期の抜け毛が多すぎる場合、以下のような健康トラブルが関係している可能性があります。。
抜け毛が関係している主なトラブル
1. 皮膚病(真菌・細菌・ノミ・ダニなど)
- 皮膚が炎症を起こし、かゆみやフケを伴うことが多い。
- ノミやダニが原因で強いかゆみが生じ、過剰に毛づくろいすることで毛が抜ける。
- 真菌(カビ)の感染によって円形脱毛が見られることもある。
2. ホルモンバランスの乱れ(甲状腺の病気など)
- 甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう):高齢の猫に多く、過剰なホルモン分泌により抜け毛が増え、毛がパサつく。
- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群):ホルモンの異常により、皮膚が薄くなり毛が抜けやすくなる。
3.ストレス
- 環境の変化や騒音、他の動物との関係がストレスとなり、過剰なグルーミングによる抜け毛につながることがあります。
4. 過剰な毛づくろい
- 過剰な毛づくろいによって、特定の部分の毛が薄くなる「心因性脱毛」が起こることもある。

うちの猫も、過去に毛繕いをしすぎて一部分が禿げてしまったことがありました…
5. 毛球症(もうきゅうしょう)
- 抜け毛が多いと、毛づくろいの際に大量の毛を飲み込んでしまう。
- 胃や腸に毛が溜まり、吐き出せずに腸閉塞を引き起こす危険がある。
- 毛球症の症状として、食欲不振、便秘、頻繁な嘔吐が見られることがある。
これらの兆候が見られる場合は、獣医師に相談し、適切なケアを行うことが重要です。
換毛期が長い・抜け毛が多いときのチェックポイント

トラブルが起きているかどうかって、どうやって判断すればいいの…?
換毛期ではなくトラブルが起きていないかを特定するために、以下の点を確認してみましょう。

これらのどれかに当てはまっているものがあれば、換毛期とは別に何かトラブルが起きている可能性があります。
抜け毛が異常に多いときの対処法

猫の換毛期が長続きして抜け毛が増えた場合は、原因に合わせて適切な対策を行いましょう。
換毛期が長続きしていると不安な方は、以下の状況別対処法を参考にしてみてください。
- 皮膚のトラブルが疑われる場合 → すぐに動物病院を受診し、原因を特定してもらう。
- 食事が原因の可能性がある場合 → 高品質のキャットフードを選び、栄養バランスを見直す。
- ストレスが関係している場合 → 落ち着ける環境を作り、遊びやスキンシップを増やす。
- アレルギーの疑いがある場合 → 環境を清潔に保ち、アレルギー検査を検討する。
猫の抜け毛が普段よりも多かったり、換毛期が長引いているときは、単なる換毛期ではなく健康トラブルのサインかもしれません。
早めに原因を特定し、適切なケアを行うことで、大切な猫の健康を守りましょう。
環境が猫の換毛期に与える影響
健康な猫であれば、春と秋にスムーズに毛が生え変わります。
ですが、猫の生活環境は換毛期の長さや抜け毛の量にとても大きな影響を与えます。
住んでいる環境が換毛期に与える影響
1. 室内と屋外の違い
屋外で過ごす猫は、自然の気温や日照時間の変化に合わせて、換毛期がはっきりしています。
一方、室内飼いの猫は、エアコンや照明の影響を受け、換毛のサイクルが乱れることがあります。
2. 乾燥や湿度の影響
湿度が低いと、皮膚が乾燥してフケが出やすくなり、毛の生え変わりがスムーズに進みません。
逆に、湿度が高すぎると、皮膚が蒸れやすくなり、細菌が繁殖しやすくなります。
猫は生活環境にとても大きな影響をうけます。
そのため、猫が幸せに生活しやすいような環境を整備することは、なによりも重要になってきます。
快適な環境を整えることで、猫の換毛をスムーズにし、一緒に住む愛猫の抜け毛トラブルを防いであげましょう。
猫の換毛期は、環境に大きく左右されます。

飼い主が適切なケアをすることで、猫の負担を減らし、健康な毛並みを維持することができます。
普段から猫の様子をよく観察し、異変があれば早めに対処しましょう。
抜け毛対策の基本!飼い主が知っておきたいケア方法
猫の抜け毛を減らすためには、日々のケアが重要です。換毛期には特に毛の生え変わりが活発になるため、定期的な手入れを行うことで、毛の抜け方をコントロールし、部屋の掃除を楽にすることもできます。
抜け毛予防に有効な定期的な手入れ
抜け毛予防には、有効的なお手入れがあります。
今回は、その中でも3つの重要なお手入れについて解説していきます。
1.ブラッシング

ブラッシングをするメリットには、以下のようなものがあります!
- 抜け毛を減らし、換毛期の毛の飛び散りを防ぐ
- 毛玉や絡まりを防ぎ、飲み込む毛の量を減らす
- 皮膚の血行を良くし、健康な毛の成長を促す
- 皮膚の異常(湿疹・ダニ・傷など)を早期発見できる
- 飼い主とのスキンシップが深まり、猫のストレス軽減にもなる
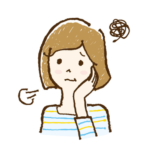
うちの猫はあんまりブラッシングが好きじゃなさそう…

猫によってはブラッシングが好きな子、嫌いな子もいます。
また、猫にもブラシの好みがあるんです!
短毛猫のブラッシングについては、過去に解説しているのでこちらも参考にしてください!
短毛種のブラッシング方法とおすすめの道具
短毛種(例:アメリカンショートヘア、ロシアンブルー、マンチカンなど) は毛が短いため、基本的に毛玉ができにくいですが、抜け毛は多くなります。
特に換毛期は抜け毛が増えるため、こまめなブラッシングが必要です。
短毛猫のブラッシングについては、以下の記事でも解説しています。参考にしてみてください!
- 頻度:週3〜4回(換毛期は毎日)
- ブラシの選び方:短毛種には、皮膚を傷つけにくい柔らかめのブラシが適している
- ブラッシングの方向:毛の流れに沿ってやさしくとかす
短毛猫におすすめのブラシや道具
- ラバーブラシ(シリコンやゴム製)
- 皮膚をマッサージしながら、抜け毛をしっかり取れる
- 静電気が起きにくく、短毛種の毛を絡め取るのに最適
- 獣毛ブラシ(豚毛や馬毛)
- 毛の表面のツヤを出すのに効果的
- 仕上げ用として使うと、猫の毛並みが美しくなる
- コーム(目が細かいタイプ)
- 抜け毛をしっかり取り除き、皮膚の異常もチェックできる
- 仕上げ用として使うと、余分な毛を取り除ける
短毛猫のブラッシングについてもっと知りたい方は、こちらも参考にしてください!
長毛種のブラッシング方法とおすすめの道具
長毛種(例:ペルシャ、メインクーン、ラグドールなど) は、毛が絡まりやすく、毛玉ができやすい特徴があります。毛玉ができると皮膚病の原因にもなるため、 こまめなブラッシングが必須 です。
- 頻度:毎日(換毛期は1日2回が理想)
- ブラシの選び方:毛の絡まりをほぐしやすいものを選ぶ
- ブラッシングの方向:毛の流れに沿ってとかし、絡まりがある部分は丁寧にほぐす
長毛猫におすすめのブラシや道具
- スリッカーブラシ(細かいピンがついたブラシ)
- 皮膚をマッサージしながら、抜け毛をしっかり取れる
- 静電気が起きにくく、短毛種の毛を絡め取るのに最適
- ピンブラシ(先端が丸い金属製のピンが並んだブラシ)
- 毛のもつれを防ぎ、毛並みを整えるのに適している
- 長毛種の毛をふんわりさせる効果もある
- コーム(目の粗いもの)
- 抜け毛をしっかり取り除き、皮膚の異常もチェックできる
- 仕上げ用として使うと、余分な毛を取り除ける
私が長毛猫のブラッシングにオススメするのは、「Alpha Muse」のペット用ブラシです!

- 柔軟で先端が丸ピン加工されている針のため、肌を傷つけにくい
- ワンプッシュで毛を捨てることができる
- 耐久性が高い
- グリップが持ちやすく、重さも115gと超軽量

効果的なブラッシングのコツ

短毛種・長毛種ともに、正しいブラッシング方法を知ることで、猫のストレスを減らしながらケアできます。
猫にブラッシングをする場合には、上記のようなコツを意識することが大切です。
また、特にブラッシングをするべき部位というのも存在します。
猫にとってブラッシングが楽しい時間になるよう、 優しく丁寧にケアしてあげましょう。
正しくブラッシングを行えば、抜け毛を減らし、健康な毛並みを維持することができます。
2. シャンプーの活用
猫は自分で毛づくろいをするため、頻繁にシャンプーをする必要はありません。
しかし、毛が抜けやすい換毛期にシャンプーを取り入れることで、余分な毛を落として抜け毛の飛散を抑えることができます。
シャンプーをするときの注意点は以下の通りです。
- 頻度:1~2ヶ月に1回(換毛期は月1回程度)
- 低刺激の猫専用シャンプーを使用する
- 乾かすときはしっかりタオルドライし、ドライヤーの温風は弱めに
シャンプーが苦手な猫には、蒸しタオルやシャンプータオルで体を拭いてあげるのも、余分な毛を取り除くことができます。
長毛猫にシャンプーをしない場合に起こる5つのリスクについて、過去の記事で解説しています。
ぜひ参考にしてみてください!
3. 食事と水分補給で健康な毛を維持
毛の健康は食事によって大きく左右されます。
栄養バランスの取れた食事を与えることで、毛の生え変わりをスムーズにし、余分な抜け毛を減らすことができます。
抜け毛を減らす食事のポイント
- 高たんぱくのフード:毛の主成分はたんぱく質なので、良質な動物性たんぱく質が必要。
- 必須脂肪酸(オメガ3・オメガ6)を含むフード:毛のツヤを良くし、皮膚の乾燥を防ぐ。
- ビタミン・ミネラルを補給:ビタミンAやEは、毛の成長を助ける。
- 水分補給箇所を増やす:水が飲める場所を数箇所追加しておく
また、十分な水分・栄養を摂取することで皮膚の健康を保ち、抜け毛を防ぐことができます。
特にドライフード中心の猫は、積極的に水を飲む習慣をつけることが大切です。

抜け毛を減らすためには、 定期的なブラッシングやシャンプー、食事管理 が欠かせません。
換毛期には、これらのケアを徹底することで、スムーズに毛が生え変わり、抜け毛の悩みを軽減できます。
日々の小さな積み重ねが、猫の健康な毛並みを守るポイントです。
部屋の掃除やハウスダスト対策のコツ
猫の換毛期には、抜け毛が部屋中に散らばり、さらにハウスダストや花粉なども気になる時期です。
部屋を清潔に保つことは猫の健康にも直結しますので、定期的な掃除とハウスダスト対策が重要です。
ここでは、効果的な掃除方法と対策を紹介します。
1. 定期的な掃除
部屋の掃除をこまめに行うことで、猫の抜け毛やハウスダストを減らし、快適な生活環境を作ることができます。
猫が家にいるときは、以下のポイントを意識して掃除を行なってみてください!
- 毎日の掃除
- 部屋の中を毎日軽く掃除機をかけることで、抜け毛やホコリが溜まるのを防げます。
- 特に猫がよく過ごす場所(ベッドやソファ周り)は重点的に掃除しましょう。
- 週に1回の大掃除
- フローリングやカーペット、カーテンなど、普段掃除機が届きにくい部分も含めて掃除します。
- 布製のソファやクッションなどは、掃除機のヘッドを変えたり、ブラシを使ったりして毛を取り除きます。
2. ハウスダスト対策の方法
ハウスダストの原因となるものは、猫の毛だけでなく、環境にあるさまざまなアレルゲンも関係しています。これらを減らすために、次のような対策が有効です。
ハウスダスト対策のポイント
- 空気清浄機の活用
- 窓や換気の工夫
- 布製のアイテムを減らす
3. 猫の寝床や遊び場所の管理
猫が過ごす場所も、換毛期中は特に注意が必要です。

寝床や遊び場が清潔であれば、猫も快適に過ごすことができます!
✅ 寝床の掃除方法
- 寝床やクッションを週に1回洗う
- ふわふわの寝床やクッションは、定期的に洗うことで清潔に保てます。
- 洗えるカバーを使用するのも便利です。
- 猫用ベッドやおもちゃの洗浄
- 定期的に猫が使うおもちゃやベッドも掃除し、毛が溜まらないようにしましょう。
- 使い終わったおもちゃは、こまめに毛を取り除いて清潔に保つことが大切です。

猫のためにも、お気に入りのクッションやベッドは定期的に洗ってあげましょう!
猫の換毛期には、抜け毛やハウスダストが増えるため、部屋の掃除とダスト対策をしっかり行うことが重要です。
猫が快適に過ごせるよう、清潔な環境作りを意識して、抜け毛やハウスダストの対策をしましょう。
猫の換毛期に役立つ飼い主向けコラム
ここからは少し角度を変えて、私たち人間目線から見て、猫の換毛期とどういう心構えで向き合って行くべきかを解説していきます。
猫の抜け毛にイライラしないための心構え
猫の抜け毛は、飼い主にとってはどうしても悩ましい問題です。
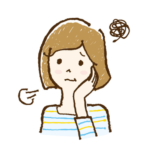
部屋中毛だらけで掃除が大変…
このような悩みが出てきてイライラしてしまうこともありますよね。
今回は、猫の抜け毛に対するイライラを少し軽減する心構えと、抜け毛を気にせずに楽しく過ごす方法を紹介します。
1. 抜け毛は自然なことだと理解する
猫の抜け毛は、換毛期に特に多くなる自然な現象です。猫が季節に合わせて毛を抜くのは、体調を整えたり、気温に対応するためです。これを理解することが、イライラを減らす第一歩となります。
✅ 心構えのポイント
- 換毛期は毎年起こること
- 猫の毛が抜けるのは、年に数回の換毛期が原因です。この時期を乗り越えれば、また毛が生え揃います。
- どうしても毛が気になる場合は、こまめに掃除をすることで落ち着いて対処できます。
- 猫が健康である証拠
- 抜け毛は、猫の健康状態が良い証拠でもあります。健康な猫ほど、季節の変化に合わせて毛を換えるので、体調の変化を感じやすい時期です。
2. 猫との時間を楽しむ
抜け毛のことを考えすぎると、猫との生活が楽しくなくなってしまいます。抜け毛を気にするあまり、猫との絆を深める時間を減らさないようにしましょう。猫との時間を楽しむことが、ストレスを減らす大切なポイントです。
✅ 猫との時間を楽しむ方法
- 抜け毛のある生活を楽しむ
- 抜け毛は仕方のないことです。猫との時間を楽しみながら、その一環として毛が抜けることを受け入れましょう。
- との遊びやお昼寝を楽しむことで、毛のことが気にならなくなるかもしれません。
- 猫に優しく接する
- 猫は抜け毛が多い時期でも元気で過ごしています。抜け毛のことにばかり気を取られず、猫の健康状態や幸せな時間を大切にしましょう。
猫の抜け毛はイライラすることもありますが、心構えと対策を工夫することで、ストレスを減らすことができます。

掃除は大変だけど、抜け毛は健康の証なんだと割り切ります!

換毛期は、どんな猫も必ずくるものです。
受け入れて、猫との幸せな時間を楽しみましょう!
猫の抜け毛掃除に効果的な掃除機の選び方
猫の抜け毛を取りやすい掃除機を選ぶことで、掃除の効率が上がり、日々の掃除のストレスが軽減されます。猫の毛は細かくて絡まりやすいため、吸引力や専用機能が重要です。
掃除機選びのポイント
- 強力な吸引力
- 猫の毛は細くて軽いため、吸引力が強い掃除機が効果的です。吸引力が強ければ、猫の毛をしっかりと吸い取ることができます。特にサイクロン式やデュアルモーター式の掃除機は吸引力が高くおすすめです。
- ヘッドの調整機能もあると便利で、床やカーペットなど、場所に応じて使いやすくなります。
- ペット用の掃除機
- ペット専用の掃除機は、猫の毛を吸い取るために特化した設計がされています。ペットの毛を取りやすいブラシがついているタイプが多く、毛が絡まって掃除機の内部に詰まることを防ぎます。
- 軽量で扱いやすい
- 猫の毛を掃除するために掃除機を頻繁に使う場合、軽量で扱いやすい掃除機を選ぶと楽に掃除ができます。特にコンパクトで手軽に使えるコードレス掃除機は、家の中を頻繁に動かすのに便利です。
まとめ
猫の換毛期は、季節の変わり目に合わせて始まり、通常は数週間から1ヶ月程度で終わります。
しかし、室内飼いの場合は、気温や照明の影響で換毛期が長引くこともあります。
そのため、飼い主としては抜け毛の対策や健康管理が重要です。

定期的なブラッシングなど換毛期の対策をしっかりと行って、私たちも猫も快適に過ごしたいですね!
抜け毛が多いと感じたら、焦らず一つ一つの対策を実践し、愛猫との生活をより良いものにしていきましょう。

