
大変だし、長毛猫はシャンプーしなくても大丈夫かな…?
そんな疑問をお持ちの飼い主さんも多いのではないでしょうか。
結論から言うと、長毛猫は必ずシャンプーをしないといけないわけではありません。
ですが、長毛猫を定期的にシャンプーしないことで、毛玉や皮膚炎、ニオイ、さらにはノミ・ダニなど、さまざまな健康リスクが生じる可能性があります。

愛猫との時間を大切にされている方にとっては、健康で長生きしてもらいたいですよね。
この記事では、長毛猫にシャンプーしないことで起こりうる5つのリスクと、シャンプーをしないでできる5つのケア方法をわかりやすく解説します。
毎日のケアで、愛猫の美しい毛並みと健康を守りましょう。
長毛猫をシャンプーしないとどうなる?5つのリスク

長毛の猫をシャンプーしなかったら、どんなリスクがあるんだろう?
結論として、長毛猫をシャンプーしない場合の一番のリスクは、皮膚トラブルです。
そんな皮膚トラブルの中でも、特に重要な健康リスクを5つ紹介していきます。
① 毛玉が増えて皮膚トラブルの原因になる
長毛猫はシャンプーなどの毛のケアをしないでおくと、毛玉が増えてしまう恐れがあります。
毛玉が増えるとどんな問題があるかというと…
上記のような問題が発生し、皮膚炎のリスクが高まってしまいます。
ここでは、愛猫の健康を守るために、毛玉ができる仕組みについて理解していきましょう。
毛玉ができやすい理由
長毛猫に毛玉ができる主な理由は以下の3つです。
- 毛が絡まりやすいため
- 長毛種の猫は、毛の1本1本が長いため、抜け毛が他の毛と絡まりやすくなります。換毛期(春・秋)は毛の量が増え、毛玉ができる確率が高まります。
猫の換毛期の抜け毛については、以下記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 毛づくろいする際に口が届かないため
- 長毛猫は、口が届きにくい部分が多いため、うまく毛づくろいができない場合があります。背中やお腹、脇の下などは特に毛玉ができやすい部位です。
- 皮脂や汚れが付着するため
- シャンプーをしないことで皮脂やホコリが毛に付着し、毛が絡まりやすくなります。皮脂が多いと毛同士がくっつき、毛玉ができる原因になります。

毛玉は放置すると悪化し、皮膚の健康に影響を及ぼしてきます。
愛猫に快適な生活をしてもらうためにも、できるだけ日頃のケアで毛玉を防ぐことが重要です。
毛玉を放置すると皮膚炎やかゆみの原因に
毛玉を放置すると、皮膚に直接悪影響を及ぼし、炎症やかゆみの原因となります。

長毛猫は被毛が厚いため、皮膚の異常に気づきにくく症状が進行しやすい傾向があります。
具体的には以下のようなリスクがあります。
- 皮膚が引っ張られ、炎症が起きる
- 通気性が悪くなり、雑菌が繁殖
- いつもより強く皮膚を引っ掻いてしまう
これらのような毛玉による皮膚トラブルを防ぐためには、次のような習慣を取り入れると効果的です。
毛玉を放置することは、猫の健康にとって大きなリスクになります。

毛玉には早めの対策を心がけて、大切な愛猫を守らないといけませんね!
②皮脂汚れがたまり、ニオイの原因に
長毛猫をシャンプーしない状態が続くと、皮脂汚れがたまりやすくなります。
皮脂汚れが溜まると臭いの原因になり、飼い主だけでなく猫自身にも大きなストレスを与えてしまいます。
長毛猫は皮脂がたまりやすい

皮脂は、毛にツヤを与えて皮膚を守る働きをしています。
長毛猫は、短毛種に比べて皮脂がたまりやすい体質を持っています。
これは、毛の長さと密度が原因で、自然に汚れが蓄積されやすくなるためです。
シャンプーをしないままでいると、毛の中に皮脂が蓄積し、べたつきや毛束になりやすい状態になります。
特に皮脂が溜まりやすい部位は
皮脂がたまった部分は毛が固まり、通気が悪くなることで皮膚が炎症を起こしやすくなるおそれもあります。
臭いが強くなることで猫自身のストレスに
皮脂汚れがたまると、においが強くなりやすくなる点も見逃せません。
人間にとって気になる臭いは、猫自身にとっても大きなストレスとなることがあります。
猫が臭いにストレスを感じる理由は以下の通りです。

できる限り、猫にはストレスを感じてほしくないですよね…
猫はことばで訴えることができないため、行動の変化に気づいてあげることが大切です。
長毛猫のにおい対策としては、以下の方法が効果的です。
においを取り除くことで、猫が落ち着いて過ごせる時間が増え、体調の安定にもつながります。
猫のこころと体の健康を守るためにも、シャンプーをしない場合はこまめなケアが必要です。
③ノミ・ダニが繁殖しやすくなる
シャンプーをしない長毛猫は、ノミやダニが寄りつきやすい状態になってしまいます。

毛の奥にたまった汚れや皮脂は、虫たちのすみかになってしまいます…
特に春から秋にかけては、ノミやダニが活発に動き出す季節です。
春や秋は、換毛期の時期でもあります。
猫の換毛期については、以下で詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください!

うちの猫は室内飼いだからノミやダニの心配はないはず…

室内で飼っているからといって安心するのは危険です!
ノミやダニは、外から人の服にくっついてきたり、ベランダ経由で侵入してくることもあります。
さらに、以下のような部位は特に汚れやすく、虫がつきやすいため注意が必要です。
これらの部分は毛が密集しており、湿気がこもりやすいです。
そのため、定期的なケアが寄生虫予防に効果的と言えます。
④抜け毛が絡まり、毛づくろいがしにくくなる
長毛猫をシャンプーしないと、普段より抜け毛が増える場合があります。
このような場合、猫の毛づくろいにマイナスの影響が出てきます。
猫のグルーミング不足が健康に及ぼす影響
長毛猫をシャンプーしないままにすると、抜け毛が絡まりやすくなります。
その結果、猫が自分で体をきれいにする「毛づくろい(グルーミング)」がうまくできなくなります。
これは猫の見た目の問題だけでなく、健康面にも悪い影響を及ぼす可能性があります。

猫にとって、毛づくろいは以下のような大切な役割を持っています!
毛がからまっていると口が毛に届かなくなり、これらの働きが十分にできません。
さらに、毛づくろいがうまくいかないことで、猫自身がイライラし、気持ちが不安定になることもあります。
飲み込んだ毛が毛球症の原因になる恐れ
長毛猫が自分の体をなめて毛づくろいする際、口に入った毛を飲み込んでしまうことがあります。
猫が毛づくろいの時に毛を飲み込んでしまうのは普通のことです。
ですが、あまりに多くの毛を飲み込むと「毛球症(もうきゅうしょう)」という病気になる可能性があります。

毛球症とは、胃や腸の中に飲み込んだ毛がたまって、毛のかたまりができてしまう病気です。
毛球症になると、次のような症状が見られます。
猫は毛玉を吐き出すこともありますが、長毛猫の場合は毛の量が多いため、うまく吐き出せずに体の中にたまってしまうことがあります。
毛球症は、シャンプーや日々のケアで防ぐことができる病気ですが、換毛期にも起こりやすい症状です。
猫の換毛期の特徴については、以下でも解説しています!
愛猫が苦しむ前に、飼い主さんのていねいなケアで健康を守ってあげましょう!
⑤猫自身の感染症リスクや飼い主のアレルギーリスクが高まる
長毛猫をシャンプーしない場合の最後のリスクは、アレルギーや感染症のリスクについてです。
長毛猫をシャンプーしないでいると、体に汚れがどんどんたまってしまいます。
その結果、雑菌やかびなどの目に見えない菌が増えやすくなり、感染症の原因になることがあります。

猫が感染症になると、どうなってしまうの…?
感染症の種類によって症状はさまざまですが、ざっくり言うと以下のような症状が出る場合があります。
- 皮ふが赤くなり、かゆがる
- 毛がごっそり抜ける
- くしゃみや鼻水が止まらない
- 傷が治りにくくなる
このような状態になると、動物病院での治療が必要になるだけでなく、猫自身も大きなストレスを感じてしまいます。
飼い主のアレルギー発症リスクも上がる
長毛猫をシャンプーしないままでいると、猫自身だけでなく飼い主の健康にも悪い影響を与えることがあります。

猫を飼っているけど、自分自身猫アレルギーという方はいらっしゃいませんか?
(私も猫を飼っていますが、猫アレルギーです)
猫の抜け毛に付着したフケや皮脂、ほこりや菌などが家の中に舞い上がりやすくなります。
結果、それらが飼い主の体に入り、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状を引き起こすおそれがあります。

長毛猫の体をきれいに保つことは、家族みんなの健康を守る第一歩になるんですね!
猫と人が安心して暮らせる環境づくりのためにも、猫のケアを心がけていきましょう!
長毛猫のシャンプー以外のケア方法5選
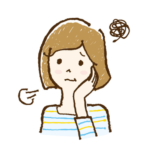
長毛猫にシャンプーをしない場合のリスクについてはわかった。
でも実際シャンプーをするのって大変…

長毛猫のケアは、何もシャンプーだけではありません!
ここからは、シャンプー以外でできるだけ楽に猫の長毛ケアができる方法を解説していきます。
① ブラッシングで毛玉と汚れを防ぐ
先に結論を言うと、シャンプー以外で長毛猫のケアをする場合、一番オススメなのはブラッシングです。
理由は単純で、ブラッシングをすることによって毛玉を防ぐことができるからです。

前にも解説した通り、毛玉は長毛猫の場合できやすく、重要な問題です。
長毛猫の場合、体に合ったブラシを使うことが効果的なケアの第一歩となります。
以下のように、用途に合わせた道具を選びましょう。
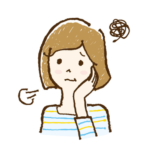
そう言われても、実際どんなブラシがうちの猫は好きかどうかわからない…

悩んだ場合、私のオススメは目が細かくて柔軟なタイプのブラシです!
目が細かいブラシは、絡んだ毛玉をほどきやすいため、長毛猫にはとてもオススメです。
そして、柔軟なブラシは肌を傷つけにくいため、猫にもとても優しいです。
私が長毛猫のブラッシングにオススメするのは、「Alpha Muse」のペット用ブラシです!

- 柔軟で先端が丸ピン加工されている針のため、肌を傷つけにくい
- ワンプッシュで毛を捨てることができる
- 耐久性が高い
- グリップが持ちやすく、重さも115gと超軽量

定期的なブラッシングを、猫の皮膚に優しいブラシで行なって、猫の健康を守ってあげましょう!
②ウェットシートで体を拭く
市販のペット用シートを活用する
シャンプーの代わりに、ペット用のウェットシートで猫の体を拭いてあげるのは、皮膚トラブルに対してとても効果的です。

なんといっても、猫にシャンプーをするより圧倒的に楽です!
ただし、1つ注意点があります。
なぜなら、猫にとって刺激となる成分(アルコールや香料など)が含まれていることがあるためです。
ペット用シートを選ぶ際は、以下の点に注目すると猫のためにも安全です!
猫のペット用ウェットシートを正しく選ぶことは、猫の体の快適なケアにつながります。
効果的な拭き方と注意点
ペット用ウェットシートを使う際、拭き方や順番にも工夫が必要です。
力任せにこすったり、苦手な場所から拭いたりすると、猫が嫌がってしまうこともあります。

猫の気持ちに寄り添った拭き方をしてあげてください。
具体的には、以下の順番で拭くのが効果的です。
- 顔や頭まわりは避け、背中や腰などの広い部分からスタート
- 毛の流れにそって、やさしくなでるように拭く
- 最後に足やお腹など、敏感な部分を手早く済ませる
そして、以下の点に注意して拭いてください!
このように、ペット用シートを使うときは、正しい手順とやさしい気配りで拭くことが猫のストレスを減らし清潔を保つ秘訣です。
③ノミ・ダニ対策を徹底する
長毛猫にはノミやダニがつきやすいため、シャンプーをしない場合は対策する必要があります。
シャンプーなしでもできるノミ・ダニ予防
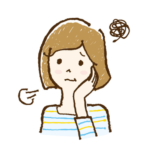
シャンプーはあまりしたくないけど、ノミとかダニがつかないか気になる…
長毛猫にとって、ノミやダニはとてもやっかいな存在です。
とくにシャンプーをしない場合、皮膚や被毛に寄生しやすくなり、かゆみや病気の原因になります。
しかし、毎回お風呂に入れるのは結構難しいものですよね。

そこで重要になるのが、シャンプーを使わなくてもできる予防策を知っておくことです。
ノミやダニを予防するためには、普段から対策を行なっておくことが重要です。
- 毎日のブラッシングで、ノミやダニがついていないかを確認する
- 部屋の掃除をまめに行い、カーペットやクッションも清潔に保つ
- 春から秋にかけては、特に予防の意識を高める
- 猫がよく寝る場所は、こまめに日干しをして湿気を飛ばす
これらの対策を続けることで、ノミ・ダニが寄りつきにくい清潔な環境になっていきます。

私たちと猫が快適に過ごすためには、日々頑張って清潔さを保つのが大切ですね!
ノミやダニの安全な駆除方法

万が一猫にノミやダニがついてしまった場合でも、安全な方法で駆除することが大切です。
焦って強い薬を使ったり、自己判断で処置すると、かえって猫の健康を損ねてしまうこともあります。
もし猫の体にノミやダニを見つけたら、以下のような対処をおすすめします。
猫用のダニ・ノミ予防スプレーを使う
→ 無香料・無着色で、肌にやさしい成分を選ぶことが大事です
動物病院で処方されるスポットタイプの駆除薬を使用する
→ 首元にたらすだけで効果が続くタイプが多く、体に負担をかけにくいです
市販のノミ取り櫛(くし)でゆっくり丁寧にすき取る
→ 特に耳の後ろや首元、お腹などを重点的にチェックするとよいです
また、駆除の際には次の点に気をつけてください。
愛猫の健康を守るためには、「気づく・予防する・正しく対処する」の三つがそろって大切です。
特にシャンプーを使わないケアを選ぶ場合には、この基本を忘れずに実行していきましょう。
④食事改善で皮脂汚れを軽減する

食事を改善することで、皮脂を減らす効果を見込むことができます。
食事が毛並みに与える影響
シャンプーを使わずに長毛猫の清潔さを保ちたい場合、食事内容を見直すことがとても効果的です。
皮脂の分泌や毛並みの状態は、日々のごはんによって大きく左右されます。
例えば、脂っこいごはんや栄養が偏った食事を続けると、以下のような問題が出やすくなります。

体に合ったごはんを選ぶことで、自然と皮脂の分泌が落ち着き、毛並みもなめらかになります!
つまり、「洗う」こととは別に、「中から整える」ことでもトラブルを予防できるのです。
皮膚や毛を健康に保つ栄養素
皮脂の汚れや毛のからまりを抑えるためには、毛や皮膚を健やかに保つ栄養素を意識することが必要です。

ここでは猫のために特に意識してほしい栄養素を紹介します!
ごはんを選ぶときには、
「猫の年齢や体質に合ったフードかどうか」
「栄養バランスが整っているか」
を必ず確認してください。
皮脂のトラブルは、毎日の食生活から少しずつ改善していくことができます。

「洗う」ことが難しいので、「食べる」ことから始めてみます!
「食べもの」が長毛猫にとってやさしく、そして持続できるケア方法となります。
⑤シャンプーの代わりにドライシャンプーを使う
ドライシャンプーのメリットと使い方
シャンプーは時間がかかるし、猫も嫌がるし、乾かすのも大変ですよね。
そんなときに役立つのが「水を使わずに毛をきれいにしてくれる」ドライシャンプーです。
長毛猫に限らず、猫は濡れることを嫌がる場合が多く、無理にシャンプーをするとケガやストレスの原因になります。

その点、ドライシャンプーは手軽に扱えて、毛の汚れや皮脂も簡単に落とせます。
このように、ドライシャンプーは、長毛猫にとって体力的・精神的にやさしい方法です!
適したドライシャンプー選びのポイント
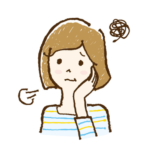
ドライシャンプー良さそうだから試したいけど、実際にはどれがいいの…
猫の体に合ったドライシャンプーを選ばないと、肌トラブルや体調不良の原因にもなりかねません。
そこで、ドライシャンプーを選ぶときに気をつけたいポイントを以下にまとめてみました!
上記ポイントを踏まえた、私のオススメはwagreet(ワグリート)さんのドライシャンプーです!
| 【楽天3冠】 水が要らない ドライシャンプー 犬 猫 シャンプー ペット用 ペット イヌ 犬用 ネコ 猫用 うさぎ用 小動物 お手入れ ニオイ 臭い 対策 ダニ ノミ ケア プッシュ ポンプ 泡で出るタイプ 泡 ドライ シャワー 安全 日本製 楽天で購入 |
このドライシャンプーのオススメポイントは…
- 楽天のランキングで9冠達成!
- 抗菌・抗ウイルスに期待できる、自然由来のティーツリー葉油・ローズマリーエキス使用
- 9つの無添加素材を使用しているため、ペットの皮膚にも優しい
- レビューが300件近くあり、他のペットに使った体験談を参考にできる

ドライシャンプーは、あくまで「補助的なケア道具」ですが、うまく使えば毎日の清潔を保つ強い味方になります。
とくに高齢の猫や病気で水を避けたい場合にも、体への負担が少なくて済みます!
長毛猫はシャンプーが大変だからしない!という方は、ぜひドライシャンプーの活用も視野にいれてみてください。
まとめ:長毛猫に最適なケア方法を選ぼう
結論として、長毛猫に水を使ったシャンプーをしない場合も、定期的なケアは必要不可欠です
長毛猫は、毛が長いために汚れや皮脂がたまりやすく、毛玉もできやすいです。
そのまま放っておくと、かゆみや病気の原因になるおそれがあります!
以下のようなケアを組み合わせることで、清潔な状態を保てます。
長毛猫にシャンプーをしない場合でも、きちんとした手入れを続ければ、愛猫の毛並みも健康も守れます。
日々の積み重ねが、大きな病気の予防につながると考えて行動しましょう!


